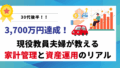担任を持った学級で初めに決めなければならないのが「学級委員長」
みなさんはどんな決め方をしていますか?もちろん「多数決」ですよね。
教員の世界で多数決を使わない日なんてないんじゃないかくらい使いまくっていますが、
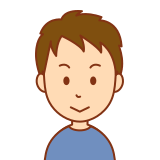
15対14で〇〇さんに決まりましたぁ!
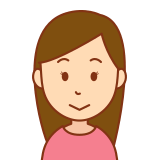
△△さんがよかったけど、多数決ならしょうがないね!
ってならないわ!!
依然の私はなんとか納得してもらうために、事前に「どんな票数でもこの結果で決めるからね」と予防策を張っていたりもしました。
でもみんなが納得しにくいのは多数決では死票が多すぎるからだと思いました。
そもそも多数決って万能なのか??国政選挙だって多数決の原理が使われているのに研究されていないわけがない!!
てなわけで検索して、余っていた楽天ポイントで購入しました。
多数決を疑う――社会的選択理論とは何か (岩波新書)
刊行日:2015/4/22
坂井 豊貴 著
収益化してないのでよくあるアフェリエイトリンクしてません。いい感じに調べて購入してください。
多数決には種類がある
わかってはいましたが、意思を取りまとめる方法はいくつかありました。
この本では、「ボルタルール」「スコアリングルール」「自由割り当てルール」「コンドルセ・ヤングの最尤法」「決選投票付き多数決」「繰り返し最下位消去ルール」という聞きなれない決め方が紹介されています。
3人の候補者がいた場合、1対1で比較すると負けてしまう(ペア全敗者)人でも、単純な多数決だと勝ってしまうことが起こるらしいです。
これまでそんなことは考えてもいませんでした。でもそれって結構やばいですよね。人がやばいんじゃなくてシステムがまずい。それに気づいている人は私の周りでは多くなかったです。
「ボルタルール」
それぞれの決め方にメリットやデメリットがありますが、その中で私が採用したのはボルタルールでした。
ボルダ‐ルール【Borda rule】
ボルダルール|Weblio デジタル大辞泉
読み方:ぼるだるーる
選挙方法の一つ。投票者がすべての候補者に対して、よいと思う順に高い点数をつけ、総得点が高い候補者を当選とする。名称は、18世紀後半にこの方法を提唱したフランスの物理学者ジャン=シャルル=ド=ボルダに由来。
参加者が3人なら、1位に3点、2位に2点、3位に1点のように配点するってかんじです。
この本を読んでボルタルールを私なりに解釈して、教室でできる実践をしました。
- 事前にクラス全員に委員長推薦者を記入させる。
- 立候補者を集めて、意思を互いに確認させる。
- 立候補者全員がクラス全員の前で、自分の気持ちを伝える。
- ボルダルールによる投票
事前にクラス全員に委員長推薦者を記入させる
クラス全員に記名式のアンケートを取ります。委員長にふさわしい人の名前を書いてもらいます。クラス名簿は事前に配っておくほうがいいでしょう(名前を書けない人もいますので)。
この時、以下のルールをアンケート用紙に記載しておき、口頭でも説明します。
- 自己推薦の場合は、それだけで立候補させる。
- 他者推薦の場合は、3票集まれば強制立候補させる。
アンケートを回収して見えないところで集計します。

Googleフォームを利用しようともしましたが、名前を記入させるとひらがなが混ざったり、チェックボックスにするにしても名前一覧を事前に読み込ませなければならないしで面倒だったので紙に落ち着いています。
立候補者を集めて、意思を互いに確認させる
立候補者を全員廊下に集めます。そこで互いの意思を確認します。
立候補者は「すごくやりたい!」「誰かに勧められればやってもいい」「他の仕事をしたいからやりたくない」などいろいろな思いを抱いています。そこを立候補者同士で確認させます。
でも、自己推薦で来たのか他者推薦で来たのかは言わなくてもいいと伝えます。
それを言うのは恥ずかしいパターンもありそうですからね。
この後に、クラス全員の前で意思を伝えます。そこで何を話すのかを考えるために数分時間を取ります。話す順番も決めてもらいます。
立候補者全員がクラス全員の前で、自分の気持ちを伝える
多数決で重要なのは、熟議です。熟議を経ずして決定することは、何も考えずにくじ引きするのと同じです。そのために候補者たちの思いを聞く場を設け、その思いと自分の思いをごちゃまぜにして考える時間を作ります。
ここで、「どうしてもやりたいからやらせてほしい!私が委員長になったら〇〇なクラスにしたいです!」とか、「絶対にやりたくないから、私には票を入れないでください」とかが始まります。

ちなみにここのターンは、漫画ハンター×ハンターの会長選挙編をイメージして設定しました。様々な思惑でミザイストムがチードルを推し、チードルがレオリオを推したように、それぞれの思惑が交錯するようにしたかったです。
ボルダルールによる投票
最後の最後にボルダルールによる投票が始まります。
候補者が4人いた場合、
1番委員長になってほしい人に4点、2番目の人に3点、3番目の人に2点、4番目の人に1点を書いてもらいます。

専用の紙を用意するのも、このあたりで面倒になってくるので、意思を伝えているときにA4用紙を細かく切って準備していますね。
黒板に4人分の名前を書いて、その横に点数を書くよう指導すると、間違いにくいです。
実績
ボルダルールは「広く支持される人」が選ばれる仕組みです。
このやり方に変えてから、クラスの中で広く支持される人が選ばれやすくなったように感じます。
多数決では「あの人を選ばないとやばいかも・・・」と生徒が思う場合もあったかもしれません。でもボルダルールだと、すべての人に点数を入れるし、その点数差も1点です。だから「あの人は1番じゃないけど、2番にしているからいいよね!」と心理的ハードルが低くなる気がしています。
そしてこの1点差がたくさんの人に起こります。結果、全体として点数差が開きます。
「うまくできているなぁ」とやりながら感心しています。
世の中には「多数決しかない」と感じやすいですが、実はそうじゃない。我々教員はそこを肝に銘じて、多数決の欠点や民主主義の本質をしっかりと伝え、考えさせなければいけないように思います。